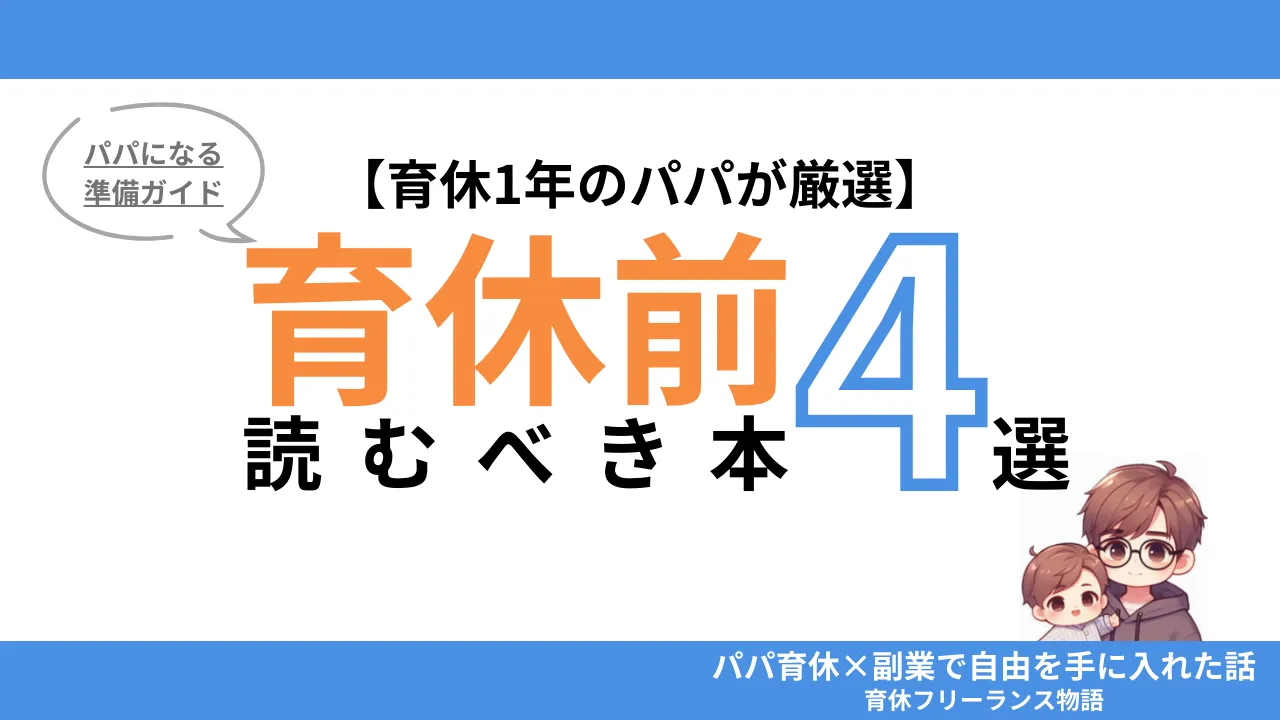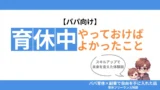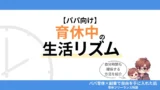- 「育休を取ることになったけど、何から準備すればいいんだろう…」
- 「パパになるって、どんな心構えが必要なんだろう…」
- 「育休前に読むべき本って何だろう…」
あなたもそんな悩みを抱えていませんか?
実は私も、育休を取得する決断をした時、まさに同じ悩みを抱えていました。
何の準備もなく突然パパになり、さらに育休という未知の領域に踏み込むのは、誰でも不安なもの。
でも、そんな時こそ本が心強い味方になりました。
今回は、超低体重出生児の父親として800gで生まれた長男の育児に奮闘し、1年間の育休を経験した私が、「これから育休を取るパパに絶対読んでほしい本」を厳選してご紹介します。
この記事を読めば、単なる「お世話係」ではなく、パートナーと協力して育児を楽しめる「頼れるパパ」への第一歩を踏み出せるはずです。

さらに、育休をきっかけに私のように人生の選択肢を広げるヒントも得られるかもしれません。
私自身、育休中にWebデザインを学び、わずか3ヶ月で月5万円の副業収入を得て、その後フリーランスとして独立。
育休が人生を変えるターニングポイントになりました。
あなたの育休も、単なる「会社を休む期間」ではなく、人生の可能性を広げる貴重な時間になるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
それでは、これから育休に入るパパに読んでほしい本を見ていきましょう!
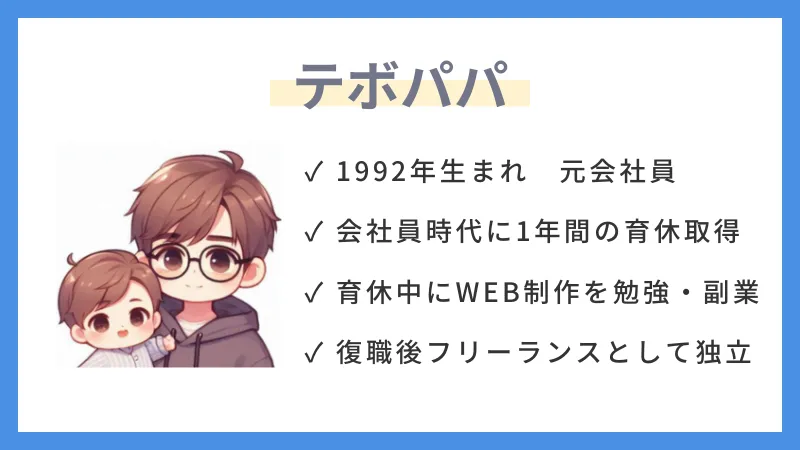
育休中にやっておけばよかったことについてはこちらをご覧ください。
パパになる準備にオススメの本4選
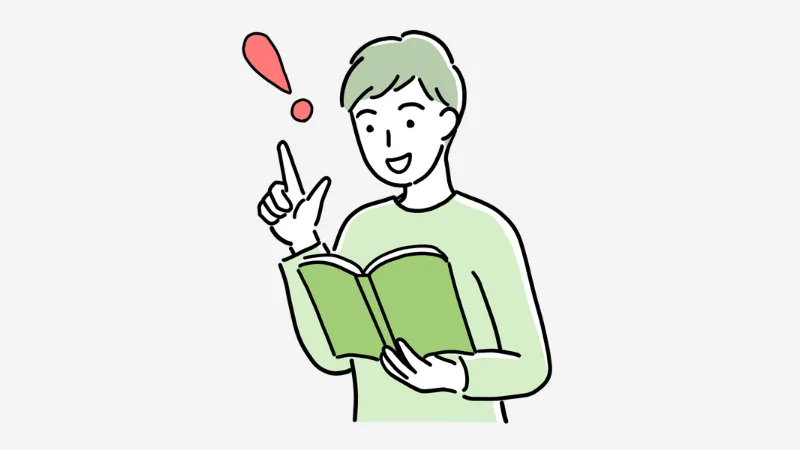
育休夫婦の幸せシフト制育児
「シフト制育児」という言葉を知っていますか?
これは単に「交代で育児をする」という以上の意味を持つ育児スタイルです。
この本は、育児を夫婦でシェアする考え方と具体的な方法を提案しています。
本書の特徴
1.具体的なシフト表の作り方
- 朝・昼・夜のシフト分けの実例
- 仕事との両立を考えたシフト設計
- 上手くいかない場合の調整方法
2.育児の「見える化」の重要性
この本の最大の価値は、育児を「見える化」する方法を詳しく解説している点です。
明確に「18時から朝1時までは私の担当」というように決めることで、お互いの責任が明確になり、ストレスが大幅に減ります。
3.夫婦のコミュニケーション改善法
本書では、育児と家事をめぐる夫婦の摩擦を減らし、チームワークを高める心構えも学べます。

シフト制育児を成功させるカギは、良好なコミュニケーションです。
私が実践して良かったポイント
我々夫婦も、この本を読んで「妻ワンオペ」、「夫ワンオペ」、「ツーオペ」の時間割を書いたシフト表を作って壁に貼りました。
これにより、「どの時間は誰の担当か」が一目で分かり、お互いの休息時間も確保できました。
特に、赤ちゃんの夜泣き対応は体力的にもメンタル的にも大変です。
私たちは「平日の18時から朝1時は妻担当、朝1時から8時は夫担当」というように明確に分けたことで、少なくとも一方がまとまった睡眠を取れるようになりました。

実際にシフト制育児を取り入れた我が家の生活を、以下の記事で紹介しているのでぜひご覧ください。
また本書では、育休中にスキルアップを図る方法についても触れられており、私がWeb制作を学び始めるきっかけにもなりました。

副業としてWeb制作を選ぶ理由を以下の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。
こんな人におすすめ
- 育児と家事の分担に悩んでいるカップル
- 「手伝う」ではなく「共同で担う」意識を持ちたいパパ
- 育休を効率的に過ごしたい人
- 育児と自分の時間を両立させたい人
本書を参考に、早い段階からパートナーとの役割分担を話し合っておくことで、育休後の生活設計もスムーズに進むでしょう。

シフト制育児の考え方は、育休明けの共働き生活でも非常に役立ちます。
嫁ハンをいたわってやりたい ダンナのための妊娠出産読本
「妊娠・出産」という人生の大イベントを、パートナーとしてどう迎えるかを優しくユーモアを交えて教えてくれる男性向けの妊娠・出産ガイドです。
専門用語が並ぶ母親向けマタニティ本とは異なり、男性視点で実体験をもとに「今、何をすべきか」がわかりやすく解説されています。
本書の特徴
1.妊娠・出産の基本知識を男性目線で解説
つわりの辛さ、検診への同行、立ち会い出産の意義など、知っているようで知らない妊娠・出産の基礎を男性にわかりやすく説明しています。

ネット検索では見つからない「夫の実際の役割」について詳しく書かれています。
2.具体的な「思いやり」の方法が満載
「何か手伝おうか?」と聞くだけでなく、「奥さんの負担を減らすために今何ができるか」を先回りして考えるヒントが豊富です。
言葉がけの工夫、体調を気遣うタイミング、休日の過ごし方など、「思いやり」の形が具体的に示されているので、すぐに実践できます。
3.夫婦の絆を深めるコミュニケーション術
妊娠期はホルモンバランスの変化で感情が不安定になりがちです。
そんな時期こそ夫婦の信頼と対話が重要です。
本書では、反発を招きそうな言葉の言い換え方や、対立時の冷静な対処法など、「円満なコミュニケーション術」も丁寧に解説されています。
私が実践して良かったポイント

第一子の妊娠がわかった時、この本のおかげで「何をすればいいのか分からない」という状態から一歩前進できました。
特につわり中のサポート例が役立ちました。
「朝食は香りの弱いものを」「洗剤の香りを変えてみる」といった細やかな配慮のアドバイスを実践したところ、妻の表情が和らいだのを覚えています。
また、長男は出産予定日の4か月前に生まれた超低出生体重児。
出産の際も、突然妻が違和感を覚え、救急車で病院に行きました。
動揺しましたが、この本で「妊娠・出産はどんなことがあるか分からない」と知っていたからこそ、パニックにならずにすみました。
こんな人におすすめ
- 初めての妊娠でどう行動すべきか分からないパパ
- 「手伝う」ではなく「一緒に取り組む」意識を持ちたいパパ
- 妻との信頼関係を深めたいパパ
- 産後の夫婦関係を円滑にしたいパパ
妊娠・出産は夫婦にとって大きな転機です。
夫としてどう寄り添うかによって、夫婦の将来は変わります。

「思いやりとはこういうことか」と気づかせてくれる一冊です。
パートナーと共に幸せな妊娠・出産期を迎えるための第一歩として、ぜひ手に取ってみてください。
はじめてママ&パパの育児―0~3才赤ちゃんとの暮らし 気がかりがスッキリ!
育児の実践的なハウツーを学ぶなら、この本が最適です。
特に「具体的にどうやって赤ちゃんを抱っこするのか」「ミルクの量はどれくらいが適切か」など、初めての育児で直面する疑問に答えてくれる頼もしい一冊です。
本書の特徴
1.豊富なイラストと写真で分かりやすい
抱っこの仕方やおむつの替え方など、文章だけでは伝わりにくい動作が、ステップバイステップで図解されています。
視覚的に理解できるので、実践しやすいのが特徴です。
2.月齢・年齢別の赤ちゃんの発達と対応方法
0歳から3歳までの子どもの発達段階が詳しく解説されており、「今、子どもは何ができるようになっているのか」「次に何ができるようになるのか」を理解できます。

これにより、子どもの成長に合わせた適切な遊びや声かけができるようになります。
3.トラブル対応と病気の見分け方
発熱や嘔吐、下痢など、よくある症状への対処法や病院に行くべきサインが分かりやすく解説されています。
夜中の急な体調不良でも、冷静に対応できる知識が身につきます。
私が実践して良かったポイント
私はこの本を読んで、おむつ替えや授乳の仕方を事前に頭に入れておいたことで、実際に赤ちゃんを迎えた時に自信を持って取り組むことができました。

特に最初の数週間は、この本を傍らに置いて実践していました。
また、月齢ごとの発達段階が書かれており、どういう遊びをすればよいかの指針になったことはとても役立ちました。
さらに、予防接種のスケジュールや乳幼児健診の内容なども詳しく書かれていたため、医療面での準備もスムーズに進めることができました。
こんな人におすすめ
- 赤ちゃんの世話の実践的なやり方を学びたいパパ
- 子どもの発達段階を理解したいパパ
- 緊急時の対応方法を知っておきたいパパ
- 予防接種など、育児に関連する制度や仕組みを知りたいパパ

迷ったときのガイドブックとして手元に置いておきたい1冊です。
DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール
一見、育児と関係ないように思えるこの本ですが、実は「子どもが生まれる」という人生の大きな転換期に読むべき一冊です。
本書は「人生で得た経験や思い出こそが真の資産である」という考え方を軸に、お金と時間の使い方を根本から見直す内容になっています。
本書の特徴
1.「今この瞬間」を最大限に生きるためのマネー哲学
本書の最大のメッセージは、「人生の幸福は貯金額ではなく、経験の質とタイミングで決まる」ということです。

キャリアや将来の収入のことばかりに目を向けがちな会社員にとって、“いま”家族と過ごす時間の価値を見つめ直すきっかけになります。
2.育休取得を後押しする「経験最優先」の考え方
人生には、“その時にしかできない経験”があります。
本書では、特に若い時期や子育て初期の「体験」が、将来にわたって幸福感をもたらすと説かれています。
- 子どもが小さい今しか得られない「かけがえのない記憶」を優先すべき
- 仕事は取り返せても、「家族との時間」は後から取り戻せない
- 育休で得た体験は「思い出の配当」として一生心を潤してくれる
3.お金を“貯めるだけ”の人生からの脱却を促す
「万が一に備えて」「老後が不安だから」と言って貯めるだけの人生は、本当に満足のいくものなのか?
本書は、そんな私たちの根深い不安に対して、合理的かつ大胆に「今を生きる」選択肢を提示してくれます。

育休で収入が一時的に減ることがあっても、それ以上に得られる価値があると実感できる一冊です。
私が実践して良かったポイント
私は育休前にこの本を読み、「育休でキャリアが一時停止しても、子どもとの時間という得難い経験を得られている」と考えられるようになりました。
特に我が子が超低出生体重児として生まれ、NICUで過ごした経験から、「時間」の価値を痛感したのです。
また、育休後のキャリアプランを考える際も、単に「収入を最大化する」のではなく、「家族との時間も確保できる働き方」を優先したことで、結果的にフリーランスへの転身という選択ができました。
こんな人におすすめ
- 育休取得による収入減やキャリアへの影響を懸念している人
- 子育てとキャリアのバランスに悩んでいる人
- 家族との時間の価値を再認識したい人
- 育休後のライフプランを考えたい人

育児は時に大変ですが、子どもの成長は一度きりです。
この本は「今この瞬間の価値」を教えてくれます。
イマイチだった本
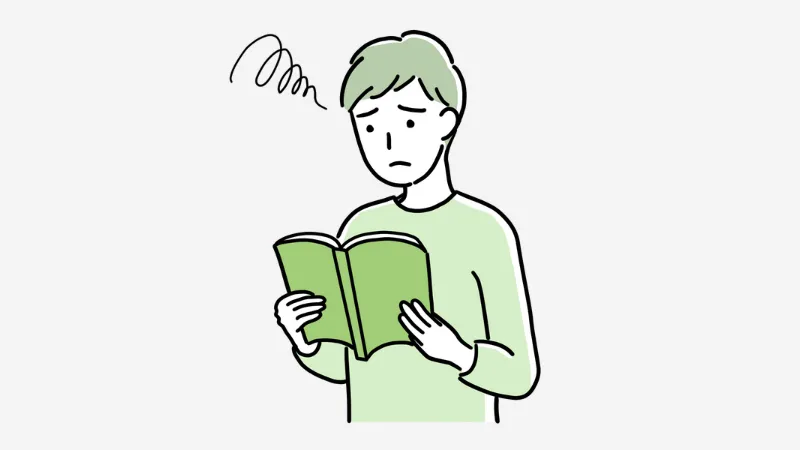
全ての本が自分に合うわけではありません。
期待したほど役に立たなかった本も正直にご紹介します。
新しいパパの教科書
NPO法人ファザーリング・ジャパンによる本書は、日本の父親たちの意識改革を目指した好著ではありますが、私個人にとっては期待したほどの実用性がありませんでした。
期待外れだった理由
1.情報が網羅的すぎて具体性に欠ける
妊娠期から子どもの就学までを幅広くカバーしていますが、それぞれのトピックが浅く触れられているだけで、実践的なアドバイスが少ないと感じました。
2.情報・価値観が古い
2013年に発行された本のため、情報・価値観が時代遅れになっています。

本書は、パパが育児を「手伝う」という意識が強く、育休を積極的に取る今の世代のパパには参考になりにくい内容です。
3.理想論が多い
「パパも育児に参加すべき」という主張は正しいですが、「どうやって」という具体的な方法論や、現実的な課題への対応策が不足しています。
こんな人にはオススメしない
- すでに育児への高い意識がある人
- 具体的な育児テクニックを学びたい人
- ロジカルに行動指針を立てたい人(ToDoリスト的な本を求めている人)
もちろん、「これから父親になる」という意識が全くない方や、育児参加の必要性を感じていない方には良い入門書かもしれません。
しかし、すでに育休を取得する決意をしているあなたには、もっと実践的な本をおすすめします。
まとめ

育休前に読んでおくべきおすすめの本4選をご紹介しました。
- 育休夫婦の幸せシフト制育児:育児・家事の分担を「見える化」し、夫婦で協力する具体的な方法を学べる
- 嫁ハンをいたわってやりたい:妊娠・出産の医学的知識を得て、パートナーを適切にサポートする方法がわかる
- はじめてママ&パパの育児―0~3才赤ちゃんとの暮らし 気がかりがスッキリ! – 育児の実践的なハウツーがイラスト付きで学べる
- DIE WITH ZERO:育休という時間の価値を再認識し、長期的なライフプランを考えるきっかけになる

これらの本は、私自身の1年間の育休経験の中で本当に役立ちました。
超低体重児として生まれた長男のNICU入院から退院後の育児、そして育休中のスキルアップを経て、最終的には新しいキャリアへの転身。
私の人生を変えるきっかけとなったのは、間違いなく「育休」という貴重な時間でした。
日本の男性育休取得率は近年上昇傾向にあるものの、育休を取得する男性はまだまだ少数派です。
厚生労働省の最新の統計によると、2023年度の男性の育休取得率は30.1%とされています。
まだまだ少数であるからこそ、先人の知恵や経験を本から学ぶことは非常に重要です。
あなたの育休が充実したものになり、子どもとの関係だけでなく、パートナーとの関係、そして自分自身のキャリアや人生観までも豊かにする機会となることを願っています。
これから育休を取るパパへ
育休は「会社を休む期間」ではなく、新しい人生の扉を開く機会です。
読書を通じて知識を得ることも大切ですが、実際に子どもと向き合い、パートナーと協力し、自分自身と向き合う時間を大切にしてください。
私のように、育休をきっかけに新しいキャリアや生き方を見つける人も少なくありません。
ぜひ、この貴重な時間を最大限に活用してください。
私は自信の経験から、育休のスキルアップ、副業としてWeb制作をオススメしています。

育休中の副業としてWeb制作がオススメな理由を以下の記事にまとめています。
ぜひご覧ください。
もし育休中の過ごし方や、育児と並行してのスキルアップについて質問や相談があれば、ぜひ問い合わせフォームからご連絡ください。
同じ経験をした先輩パパとして、できる限りサポートします!

最後まで読んでいただきありがとうございました!